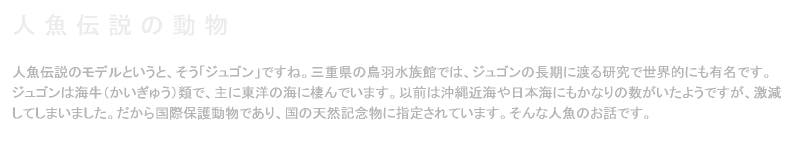人魚のモデルは海牛類
海牛類とは?
海牛類の祖先は陸上で歩き回る動物だったのですが、(どうもゾウと近縁らしく歯の仕組みが似ているそうです)好物である水辺の草を求めて、また、外敵から身を守るために、水中の生活に適応するようになっていきました。長い年月を経て脚を無くし、尾は魚のように進化し、現在のようなイルカ型の体型になったそうです。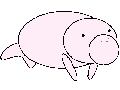
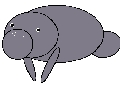
ご存じでしたか?
人魚のモデルとなっている海牛類はジュゴンだけではないんです!
実は「ジュゴン」のほかに「マナティー」がいるのです!
◆左が「ジュゴン」右が「マナティー」◆
海牛類は海や川に棲んでいる草食のほ乳動物で、世界で4種類います。その1種類がジュゴン、あとの3種類が川に棲んでいるマナティーなんです。3種類というのは棲む地域によって名前が少し変わるからなんですね。アフリカマナティー、アマゾンマナティー、アメリカ(フロリダ)マナティーです。
ジュゴン(左)とマナティー(右)の違いは、棲んでるところが違うほかに、姿にも若干の違いがあります。ジュゴンの体色はピンク色ですが、マナティーはゾウやサイと同じ褐色、尾の形がジュゴンはイルカと同じV字、マナティーは「しゃもじ」や「うちわ」のような丸形です。手はマナティーの方が少し長いです。
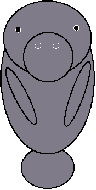
マナティーは眼に白い縁取りがあり、愛くるしい表情をするし、長い手を器用に使って大好きな水草を食べたり、顔に手を持ってきて人間くさい仕草をしたり、ほんとに可愛いんです。泳いでいる姿や表情を見ていると心が和みます。
*美ら海水族館のマナティー
マナティーのお話
マナティーには棲む地域により3種類の名前があることは紹介しましたね。写真集やテレビなどで紹介されるようなマナティーは、ほとんどアメリカマナティー(フロリダマナティー)のようです。
以前、元大関のKONISHIKIさんが、テレビの仕事でアメリカに行ったとき、マナティーに会いたいということでフロリダを訪れた番組がありました。あの大きな体のKONISHIKIさんが、こちらも大きな体のマナティーと御対面、子供のようにはしゃぐ気持、良くわかります。
マナティーは草食なんですが、ずんぐりとした肥満体型です。鳥羽水族館のオスの「かなた」は、体長3m、体重は500kg近くあり、鳥羽水族館一の巨体の持ち主。その大きな体でゆったりと泳ぐ姿は、見ていて和んでしまいます。
もともと水草が大好きなマナティー、水族館では水草ではなく、牧草やレタス、ニンジンなどを食べています。食欲旺盛のマナティーのこと、故郷では思い切り食べていたでしょうが、水族館ではどうなんでしょうか、思うように食べられているのでしょうか?心配ですね、水槽もそんなに大きくはないし、可愛そうな気がします。ちょうど、大阪の海遊館にいるジンベイザメも同じです、狭い(と私は思う)水槽の中では思い切り手足(?)を伸ばせないですもんねえ。
マナティーはほ乳類、ということで肺呼吸をしています。イルカと同じように時々水面に出て呼吸をしなければなりません。ですから呼吸の時には、水中では閉じている鼻の弁が開きます。でも、その呼吸が悲劇を呼ぶことがあるんです・・・
人魚の悲劇とは・・・
アメリカ・フロリダ半島にあるクリスタルリバーでは、マナティーの保護活動に早くから立ち上がり活動を進めている。マナティーは寒さが苦手、だから冬の間はメキシコ湾から冬でも暖かい水温を保つクリスタルリバーにやってくる。マナティーは肺呼吸なので時々水面に顔出す、また、のんびりと水面近くを泳ぐマナティーに猛スピードのレジャーボートが接触するとどうなるでしょうか?
深刻な絶滅の危機に瀕しているマナティーの死亡原因の一位、それがボートのスクリューにより傷つけられること、クリスタルリバーにやってくるマナティーのほとんどに、尾などに切り刻まれた傷が残っているのです。悲しいことにその傷が、個体識別に役立つとは・・・
現在では、保護活動が進んだこともあって、ボートのスピードが制限されたり、サンクチュアリ(聖域)ができています。子供を三年に一度しか産まないので、なかなか個体数が増えないのも激減している理由の一つ。
フロリダの観光客が増加し、マナティーの状況が知れわたると、保護活動に対する啓蒙が生まれますが、観光客が増えることによるマナティーへの影響、それだけ危険性も増加してしまうことにもなりそう。
マナティーには自然界における天敵はありません。他の動物を襲うこともありません。唯一の天敵といえるのが、我々人間なんです。それでもマナティーは人なつこく寄ってくるそうです。人間に傷つけられながらも、ひどいことされても、実に穏やかに、暖かく人間を受け入れてくれる。
地球上、最も優しいほ乳動物、それがマナティーではないでしょうか・・・